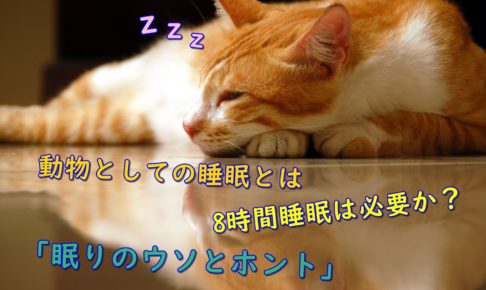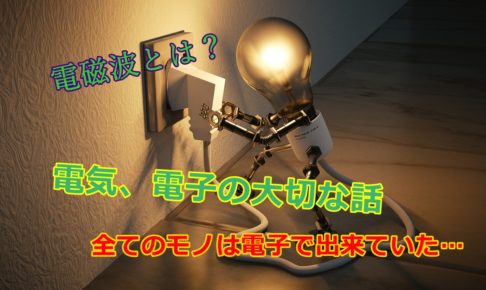ユウサク
「ワイン」と言えば、ご存知の「アルコール飲料」ですよね。
そのイメージは人それぞれですが、「毎日飲む」って人もいたり、「レストランでしか飲んだことない」なんて人もいたり…。
安くて数百円、高くて数百万…なんて「値段差の激しいモノ」である事は確かですよね…。
では、何がそんなに違うのか…。
今回はそんな「ワイン」について、基礎的な知識や 楽しみ方まで、簡単にまとめていきます。
~もくじ~
ワインとは?
ワインとは主に「ブドウ」を発酵させたモノで、酵母の発酵を用いて作られる「醸造酒」の一種です。
糖分の働きによって発酵させる「ワイン」は、ブドウ自体の水分のみで作られるため、ブドウの味や、ブドウの出来で 味が大きく変わります。
ブドウは地域性の強い植物のため、土壌や気候によって 同じ種の木を植樹したとしても、同じ実を付けるとは限りません。
そのため、「産地」や、「ブドウの育成条件(テロワールと言う)」によって、ワインの価値や、味が大きく変わってくる事になります。

ワインの起源は古く、古代エジプトの壁画や旧約聖書にも登場しており、紀元前600年頃にローマ人によってヨーロッパ全域に広められたと言われています。
そこから、16世紀の大航海時代を経て、ワインはヨーロッパから「世界全域」へと広がり、世界中で飲まれるようになっていきます。
日本では、1964年の東京オリンピックをきっかけとした「第1次ワインブーム」から現在に至るまで、年々その消費量は増え続けています。(現在は「第7次ワインブーム」らしい…)
その背景には、ボジョレー・ヌーヴォーの流行や、ポリフェノールによる健康効果、チリワインなどのワイン価格の低下(関税引き下げ)などが挙げられ、これからも日本国内での消費量は伸びていくものと予想されています。
ワインの種類
「ワインの種類」は有名なモノで、大きく分けると「スティルワイン」と呼ばれる
「赤ワイン」、「白ワイン」、「ロゼワイン」
この三種類(非発泡性のワイン)と、
「スパークリングワイン」と呼ばれるものに分けられます。(発泡性のワイン)
それぞれどんな特徴があるのか?順に見ていきましょう。
・赤ワイン
主に「赤ブドウ」や、「黒ブドウ」を原料として作られるワインで、「ブドウの実をそのまま(皮と種も)」アルコール発酵させてつくるのが特徴です。
ワインの濃い赤色は、皮の部分に含まれる色素の色で、その皮に含まれる「タンニン」という成分などによって独特の色味や、渋みが出るワケです。

赤ワインは味の種類を分ける時に、「軽い」、「重い」といった表現で表します。
・渋みが強く、濃厚で色味の濃いものを・・「フルボディ(重いワイン)」
・渋みや、酸味のバランスのよいものを・・「ミディアムボディ」
・渋みが少なく色の薄いものを・・・・・・「ライトボディ(軽いワイン)」
といったように表現し、「タンニン」の渋みによって、飲んだ時にズッシリ重く感じる事から このような表現が使われます。
次に赤ワインのボトルについてですが、光による劣化を防ぐために 赤の補色である「濃緑色」のボトルが使われる事が一般的で、「ボトルの形」で産地を だいたい見分けることができます。(または渋みの度合い)
ボルドー系の産地のものは「いかり肩」(複数品種のブドウをブレンドしたものが多い)、
ブルゴーニュ系の産地のものは「なで肩」(単一品種のブドウを使用したものが多い)、
のボトルを使っており、渋みが強いボルドー系のものは、熟成中の「澱(おり)」が瓶の中に溜まりやすく、ワインを注ぐ際に その沈殿物がグラスに注がれないようにそのような形になっています。
なので、いかり肩のボトルの赤ワインは「渋みが強い(場合が多い)」、なで肩のボトルの赤ワインは「あっさり飲みやすい(場合が多い)」と覚えておけばよいです。

・白ワイン
白ワインは主に「白ブドウ(マスカット)」や、「黒ブドウ」を使って作られますが、赤ワインと違い「種や皮を取り除いてから」アルコール発酵させてつくるのが特徴です。
マスカットを使って作るのが「白ワイン」だと思っている人も多いようですが、ブドウって皮は濃い紫でも「中身は 透明だったり薄い緑だったり」しますよね。
どちらのブドウを使った場合も皮を取り除いてから発酵させるので、色は「透明に近い黄緑色」になり、タンニンによる渋みがないため、すっきりとした口当たりになります。

白ワインは味の種類を分ける時に、「甘口」、「辛口」といった表現で表します。
・酸味が強く、味が締まったものを・・・「辛口」
・酸味が穏やかで、まろやかなものを・・「甘口」
これらは、糖分が発酵してアルコールに変化する度合いで決まりますので、ワインの中の「糖分の残量」によって違ってきます。(赤ワインでも糖分の残量、発酵の度合いを表すために表示されることも)
次に白ワインのボトルについてですが、白ワインもボトルの色で だいたいの味を見分けることもできるようになっています。
ほとんどの場合、背が高く細長い形になっていて、辛口は「薄緑色」、甘口は「透明」のボトルが使われる事が多いのが特徴です。
・ロゼワイン
「ロゼ」とは フランス語でピンク色を意味する言葉で、淡いピンクが特徴の美しい色のワインがこれにあたります。
主に、赤ワインを製造する過程で、「発酵途中に皮を取り除く」といった製造方法で作られ、そのタイミングによって色味や、味を調節する事ができます。(他にも製法はありますが、代表的なモノはこれ)
味はおおむね「赤と白の中間」で、見た目の美しさから、祝い事や、食事の席でも好まれ、今や 白ワインよりも人気のワインとなっています。

ちなみに、ボトルは綺麗な色合いを演出するため、透明なものが使われる事が多く、見た目にも楽しむことができます。
・スパークリングワイン
「スパークリングワイン」とは、「発泡性のワイン」の事で、ワインの中に「二酸化炭素(炭酸ガス)」を多く含んだものを指します。
通常のスティルワインに糖分と酵母を加えて「二次発酵」させる事で炭酸ガスを発生させる方式(きめの細かい泡が造られる、値段は高くなりがち)と、
後から二酸化炭素を吹き込む方式(泡は荒いモノが多く、安価なものが多い)のどちらかで作られます。
スパークリングワインと言えば「シャンパン」を思い浮かべますが、炭酸が入っている高価なワインが全て「シャンパン」と呼ぶ訳ではありません。
「シャンパン」とは、フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリングワインのことで、フランスの厳しいワインの法律(AOC制度)の条件を満たしたもののみが名乗る事が許された特別なスパークリングワインを指す名称です。
AOC制度とは、(appellation d’origine controlee「アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ」の略)フランスの農業製品、ワインやチーズについて定められた「品質保証」のための法です。
ブドウの品種や、決められた製法で造られること、アルコール度数が11%以上であること…などなどが、品質を保証するために細かく規定されている。
現在は、EU産の高品質産品に「AOPラベル」が義務化した事によって、AOP(Appellation d’Origin Protegee)と表示されるようになっています。

シャンパン以外にも スパークリングワインのラベルは多くあり、
フランスでは「ヴァンムスー(Vin Mousseux)や、クレマン(Crémant)」、
イタリアでは「スプマンテ(Spumante)やプロセッコ(Prosecco)」、
スペインでは「エスプモーソ(Espumoso)や、カヴァ(CAVA)」、
ドイツでは「シャウムヴァイン(Schaumwein)やゼクト(Sekt)」、
アメリカや、日本などでは、そのまま「スパークリングワイン(Sparkling wine)」など、各国それぞれの産地や名称で表示されます。(シャンパンと同じシャンパーニュ製法で作られるものも多く存在する)
・ボジョレー・ヌーヴォー
日本でもよく「ボジョレー・ヌーヴォー解禁」なんて言葉を聞くようになりました。
何で解禁日があるの? と思いますよね…?
それは、未熟なワインや粗悪なワインが出回らないように「フランス政府が解禁日を制定した」からです。
毎年 ブドウの収穫を終えた「11月の第3木曜日」に解禁されるのですが、日本でも同じように「解禁日」を待って一斉に販売するというのがルールになっています。
ちなみに、ボジョレーヌーヴォー(Beaujolais Nouveau)は、フランスのボジョレー地方で造られる新酒のことです。
ブドウの良し悪しを確認するために造られるワインで、収穫してから数週間という短時間でワインを熟成・発酵させる必要があるため、その製造方法は他のワインとは異なります。
その製法は、ブドウ自体の重みで果汁を出し、自然に発酵させるといった製法(マセラシオン・カルポニック製法)で、タンニンが少ないわりに色が濃く、渋みや苦味が通常のワインよりまろやかになります。
元々は、収穫祭を祝うための新酒だったそうですが、収穫後にすぐに飲めるワインであることや、他のワインと違ったフレッシュな飲み口が話題となり、世界中で人気になりました。
早飲みタイプのワインなので、購入後は冷蔵庫で冷やしてなるべく早く飲むとよいです。
ワインの成分
ワインにはどんな成分が含まれているのか?
健康に良いとされているポリフェノールとは?飲んだら頭痛がするって言われてるけど…?酸化防止剤って必要?
そんな気になる成分を見ていきましょう。
・ポリフェノール
ポリフェノールとは、ほとんどの植物の葉や種などに含まれている自然由来成分のこと。
強い「抗酸化作用」を持ち、病気や老化の原因になる活性酸素を身体から取り除いてくれる。と言われていて、ワインには「アントシアニン、カテキン、タンニン、レスベラトロール」といったポリフェノールが含まれています。
ポリフェノールの多くは「ブドウの皮や種」に含まれるため、ポリフェノールの含有量のみを見ると、白ワインよりも、赤ワインの方が多く含まれている事になります。
ワインには、これらのポリフェノールによって、他にも抗菌・殺菌作用や、脂肪の燃焼を促進する作用(ダイエット効果)、制ガン作用がある、とされています。
・アミン(ヒスタミン、チラミン)
ワインを飲むと頭痛がするなんて人もいるようですが、以前まではワインに含まれる「酸化防止剤」が頭痛の原因だと言われていました。
が、最近になって頭痛の原因は、ワインに含まれる「アミン」という成分のせいではないか?と言われています。
アミンは発酵食品に自然と含まれるもので、ワインには主に「ヒスタミン」と「チラミン」が含まれています。
これらは、他の発酵食品にも含まれている事が多く、チーズ、味噌、納豆、ヨーグルトなど…、他のモノでも頭痛のしたことがある人は「アミン」が原因の可能性が高いかもしれません。
・酸化防止剤(亜硫酸塩)
酸化防止剤とは、ワインの酸化を止めるために使われる「亜硫酸塩」という成分です。
ワインを作る過程で 必ず入れる必要のあるもので、どれだけ高級なワインであっても添加する必要があります。
亜硫酸塩は二酸化硫黄、亜硫酸とも表示され、二酸化硫黄には抗菌作用があるため、食品添加物として アルコール飲料や、ドライフルーツの保存料、漂白剤、酸化防止剤などに使われます。
この成分が危険だ!!と言われる事もあるそうですが…それを言い出せば日本に流通している飲料のほとんどに酸化防止剤や防腐剤、着色料などの添加物が大量に含まれている事は大丈夫なのか?と言いたくもなります…
高品質なワインを作ろうとすれば、酸化防止剤は必ず必要になってきます。
そもそも、二酸化硫黄は揮発性なので、開栓した際にほとんどが揮発して無くなってしまうと言われています。
ワインが開栓したと同時に「味が変わる」と言われるのはこのことが原因でもあるワケです。(スワリングについても酸化防止剤を揮発させる目的もある)
最近では、「ナチュラルワイン」、「無添加ワイン」といった、酸化防止剤にだけ着目して、無添加を売りにしているものもありますが…
酸化防止剤を入れないと言う事は、発酵によって生じるはずの甘みや酸味などを人工的に追加しないといけないと言う事です。
一旦加熱し、アルコールを飛ばしてから添加物で味を調節する…そんなイロイロな添加物が大量に入ったワインも世間に出回っています。
「無添加だからいい」そんな考えはまず捨てた方がよいかもしれませんよ。
ワインの味の違い
それでは、次にワインの味の違いを決める要素を順に見ていきます。
先の項にも書きましたが、ワインの味の違いは、ほぼ「ブドウの出来の違い」になります。
なので、ワインを選ぶ際には「ブドウの産地がどこであるか?」がとても重要視されるワケです。
ワインの歴史の古い、ヨーロッパや地中海沿岸の伝統的な産地のモノを「旧世界のワイン」と呼び、
ワイン生産の歴史が比較的新しい産地、新しくワイン文化を作り上げた産地のモノを「新世界のワイン」と呼んだりもします。
ちなみに、旧世界と呼ばれる地域は、ワインの定番の国、フランス、イタリア、スペイン、ドイツなど。
新世界と呼ばれる地域は、アメリカ、チリ、オーストラリア、日本などで、日本のワインブームのきっかけは新世界のワインが手軽に手に入るようになったから…と言うのも大きな要因になっています。
・産地の違い
まず、ワイン生産量の多い産地の特徴をいくつか見てみましょう。
「フランス」
「ボルドー」や「ブルゴーニュ」、「アルザス」、「シャンパーニュ」など、有名なワインの産地が多く存在する「ワイン大国」と呼ばれるフランス。
世界のワイン生産量の約20%を占め、ブドウ栽培に適した温暖な気候と大地があり、高品質なブドウを安定的につくれる場所として有名です。
品質の高さと、個性を維持するための歴史と伝統を守り、「ワインの歴史」を先導してきた国でもあります。
高い品質で知られる「ロマネ・コンティ」や、「ドン・ペリニヨン」もフランスのワイン。
「イタリア」
世界1のワイン生産量を誇り、フランスよりも長い歴史を持つと言われるイタリア。
地方によって様々な特徴のあるワインが楽しめる事が有名で、約20万種類以上のワインの種類(ラベル)があると言われています。
「水よりも安い」手軽に飲めるワインから、マニアックなワインまで、実に幅広い個性的なワインが存在します。
「スペイン」
世界第3位の生産量を誇るスペインは、赤ワインの生産量が多く、有名なものでは、「シェリー」といった「酒精強化ワイン」など。(ブランデーなどのアルコール度数が高いお酒を加えて作るワイン)
アルコールの強いモノや、酸味の強いワインも多く、果実やジュースを混ぜる「サングリア」といった飲み方をするのもスペインの特徴とも言えます。
スペイン産のスパークリングワインである「カヴァ」も本格的なスパークリングワインでありながら、コスパがいい事で人気を集めています。
・熟成について
ワインと言えば「ワインセラー」などを使って 長期保存して熟成させるイメージを持っている人もいると思いますが、単純に年代が古ければ美味しいというわけではなく、必ずしも熟成させれば美味しくなる。というモノでもありません。
ワインは樽から瓶に移した状態でも熟成し続けるため、元となるブドウの状態、育成状況によって「飲み頃のピーク」というものが変わってきます。
ワインは熟成させる事によって、ワインの渋み成分である「タンニン」が変化して、味が変わっていきます。(なので、タンニンをあまり含まない白ワインは熟成させにくい)
そのため、天候に恵まれて育った良質なブドウは「タンニン」が多く含まれるため、熟成させた方が美味しいとされ、逆に 天候に恵まれず育ったブドウは「タンニン」が少ないため、早めに飲む方が美味しいとされます。
なので、「ワインの飲み頃」は、当たり年のワインは熟成してピークを迎えるまで待ってから飲む。
それ以外のワインはピークを早く迎えるため1~2年以内に飲む。といった感じになります。
ブドウの育成はとてもデリケートで、天候状態によって育成状況が大きく変わります。
良い天候状態の年に「良い環境で育ったブドウ」を使ったワインを「当たり年のワイン」といった表現をします。
「飲み頃」は人によって変わる抽象的なモノですので、特別なワインでない限り「熟成させる必要はなく」早く飲んだ方がおいしいと言えます。
ちなみに、長い熟成に耐えるものを「長熟タイプ」、逆に早く飲むものは「早飲みタイプ」といいます。
・ワインの温度
ワインを飲む際、ワインの温度には「適温」があります。
これは、ワインの味を引き出すための温度なのですが…(ワインの味が変わる訳ではないので必死になって温度計を差し込むような恥ずかしい事はしないようにwww)
適温だと言われている温度は、あくまで「飲みやすく感じる温度」です。
ワイン自体の味が変わる訳ではなく、ワインの「味を感じる感覚」が変わるだけです。
タンニンの強い「渋みやコク」のあるワインは、高めの温度が渋みを抑えて感じれるから良いとされ、
逆に、甘口の白ワインは、その甘さを和らげるために低い温度で飲むといいです。
お茶が冷めると苦く感じる、コーラが温かいと甘く感じる、この味覚の感覚を和らげるための温度管理です。
好みもありますので、そこまで厳密に管理する必要はありませんが、ワインを飲むときの温度の目安は以下のようになります。
- 渋い、またはコクのある「重めの赤ワイン」:15~18℃
- さっぱりとした「軽めの赤ワイン」:10~14℃
- キリっとした「辛口の白ワイン」:7~14℃
- 甘めの「甘口の白ワイン」:5~8℃
温度を変える事で、ワインの味はかなり変わって感じます。
「渋み」、「酸味」、「甘味」をバランスよく感じる温度が適温と言われますので、自分が飲みやすいと思う「自分好みの温度」を見つけるのがいいでしょう。
ワインの値段の違い
ワインには数百円のリーズナブルなモノから、数百万円もするようなものまで…様々なモノが存在しますが、いったい何によって決まっているのでしょうか。
まずは、ブドウの育成にかかるコストの違い…。
手摘みと機械で摘む場合、同じブドウだったとしても、手摘みの方が時間がかかります。つまり、コストがかかるという事です。
栄養の配分を考えたクオリティの高いブドウを作るためには、剪定や房切り作業によって収穫できる葡萄の実の数を減らします。
高級なワインなどはブドウの収穫高を1/10くらいまで落として一房当たりのクオリティを高めるのだそうです。
もちろん出来るワインの量も1/10になる訳ですから、ワインの値段は10倍以上になってしまいます。
他には、産地の違い、天候条件の違いなどが挙げられますが…元は同じブドウです。
大きな値段の違いは、ほぼ「ブランド」と、「希少価値」の違いと言えます。
なので、高いワインと、安いワインの味の差なんて、素人には分かり得ませんww
高いワインを飲んでも自分の舌に合わなければ おいしく感じませんし、有名な産地のモノ以外にも「こだわって作られた数千円のワイン」だっていくらでもあります。
・安すぎるワインに、高すぎるワイン
最近では、本当に安いワインがスーパーなどでも見られるようになりました。
ですが、安すぎるワイン…ちょっと安すぎやしないかい?と思いませんか?
ワインには輸入の際にかかる「関税」と、国内の酒類にかかる「酒税」、「消費税」などの税金がかかります。
他にも「輸送費」、「ボトル代」、「ワイナリーの利益」など、必ず必要になる「経費」がかかってきます。
ここで、原価という観点からワインを見てみます。
例えば、これらの「経費」に 500円が必ずかかるとします。
1000円のワインでは、その内の500円が中のワイン自体の値段…
10000円のワインでは、その内の9500円が中のワイン自体の値段…
では、550円のワインでは…中のワインには50円しかかけられない事になってしまいますよね…?
確実にかかる「経費」と、ワインの「原価」を考えて「安すぎるワイン」は選んだ方がよさそうです…
ちなみに高すぎるワインにも注意が必要です、最近では「偽造ワイン」と呼ばれるモノも多く出回っていると言われています。
ちょっとラベルを変えるだけ…中身を変えるだけ…そんなモノも多く出回っているという事です。
宝石などと同じように、素人にはほとんど中身の分からないモノですからね…。
高価なワインを購入の際はこういった事にも気を付けて選ぶ必要がありそうです…(まあ、わたしのような一般市民には関係のない話ではありますが…www)
・ワインのウンチクは捨てよ
日本人は特に「値段や、ブランド」なんて表面的な事に敏感です、高いと美味しい、安いとまずい、なんて勝手に決めつけてしまいがちです。
本来ワインとは世界的に見れば日常的に飲まれる飲料で、「安い」のが基本です。逆に「高い」ものは例外的なワインです。
本当においしいワインを飲みたいのなら…、「ウンチクは捨てよ」と誰かが言っていましたね。
そんな格式や、マナーなど、誰かが決めたモノに縛られて本当の味を感じられないのならば、そんな無駄な知識は捨て去った方がマシだという事です。
高級なモノ、有名な産地のモノだけが美味しいと決めつける必要はありません。
ワインを格式高いモノにしたいと思うのは、一部の「高級志向の金持ち」や、「ワイン投資家」、「ブランド化したいワイナリー」などの思惑でしかありません。
そんなウワベに流されずに、自分の美味しいと思ったモノを探して飲めばいいのです。
それが、本来の「ワインの楽しみ方」なのですから。
まとめとか感想とか
わたし、実はあまりお酒は強くありませんし、あまり飲めません!!
なので、ワインの味をどうこう語れる資格はないだろう と言われてしまいそうですが…
ワインは、人それぞれの楽しみ方があります、色や香りを楽しんだり、コレクターのように年代物を集めてみたり、毎日ガバガバ飲んでみたり…
様々な楽しみ方があるからこそ、奥の深い「嗜好品」なんだと言えるのでしょう。
誰かの価値観に合わせる必要はありませんし、誰かのマネをする必要もありません。
自分なりのワインの楽しみ方を見つければいいとわたしは思います。
ではでは、今回はここまで。また次の記事で会いましょう。
迷った羊の疑問

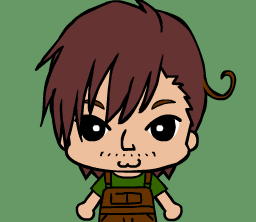
主に熟成させたワインや、テイスティングの際に必要な事で、飲食店でソムリエが入れてくれるような飲み頃のワインは回す必要がないからね。www

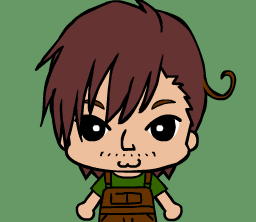
料理とワインの結婚にたとえて「マリアージュ」って呼ぶらしいよ。
ワインを選ぶ時は料理に合わせる事で、よりお互いの味を引き出せるんだって。
料理と素材の色を合わせるといい。とか、こってりした料理には重いワインが合うとか…まあ、あまり難しく考えずにイロイロな組み合わせを楽しむのも いいかもしれないね。

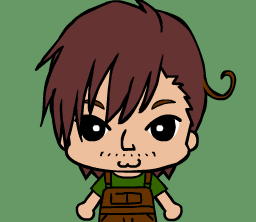
まずは、産地やブランドにはそんなに「こだわらずに」、自分がどんなワインを美味しいと感じるのか?そのワインが重いのか、軽いのか?甘いのか、辛いのか?そんな事を考えて選んでみるといいんじゃないかな?
高いワインの味を知っておく事も重要だけどね。