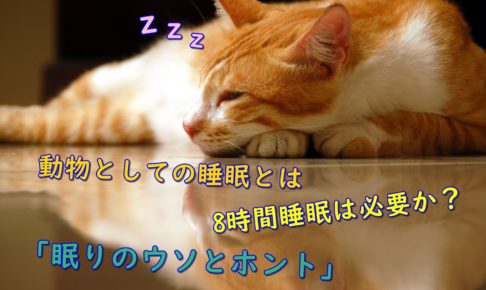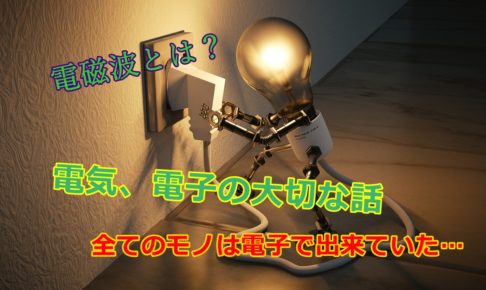ユウサク
「紅茶」と言えば、みなさんご存知だと思いますが、実は紅茶って世界中で愛飲される飲み物で、世界で作られる「お茶」の約7~8割は「紅茶」なんだそうです。
日本ではコーヒーの方が人気があるようですが、「コーヒー嫌い」がいても「紅茶嫌い」はあまり聞きませんね。
それだけクセのない飲み物だとも言えます。
ですが、日本では「普段から紅茶を飲むよ!!」って人でさえ ペットボトルや、インスタント のものばかり…と言うのも現状です。
紅茶は「渋い味の飲み物」といった印象が強いようですが、それは「お茶の選び方」と「お茶の淹れ方」を間違えている可能性があります。
本当においしい紅茶には渋みは少ないですからね。
「本当の紅茶の味」知っていますか?
淹れ方や、産地、ブランド、などによって味や香りも全く違うものになります。
奥深い楽しみ方がある。だからこそ「嗜好品」と呼ばれたり、「上質なティータイム」なんて言葉があるのです。
今回はそんな紅茶について、簡単にまとめていきます。
~もくじ~
紅茶とは
紅茶は、「カメリア・シネンシス」と言う茶樹から取れる茶葉を使って、その葉を発酵させたものです。
発酵と言っても、醤油や味噌、お酒、などのように「細菌発酵」ではなく、タンニンを酸化させる事による「酸化発酵」といった方法で作られます。
実は、紅茶は「緑茶」や、「烏龍茶」と同じ茶葉から作られます。

緑茶や、烏龍茶との違いは、発酵の度合いの違いで、
緑茶: 発酵させない(不発酵茶)
烏龍茶:少し発酵させる(半発酵茶)
紅茶: 完全に発酵させる(完全発酵茶)
といった分類で分けられます。
緑茶は熱を加えて酸化酵素(こうそ)の働きを止め、そのまま製茶します。
紅茶は茶葉を揉捻(擦り揉み)することによって、酵素(こうそ)を空気に触れさせて酸化発酵させます。
そうする事で、あの 香りや、色合いが出て来る訳です。
本来は、「カメリア・シネンシス」の茶樹から採れた茶葉を使って淹れるもの のみを「お茶」と言います。
なので、ハーブを使った「ハーブティー」や、そばの実を使った「そば茶」などの穀物茶、「柚子茶」や、「昆布茶」など、「茶」と付く それらは厳密には「茶」とは呼ばないそうです。
何かから抽出したものや煮出したものを「茶」と言う。そんなイメージから形式的にそう呼ばれている、と言うことなんだそうですね。
紅茶と聞くと、ヨーロッパ辺りから伝わった飲み物かな?なんて勝手にイメージしてしまいますが、紅茶は実は中国から伝わったものです。(もちろん緑茶も)
元は、中国の緑茶や、烏龍茶が原型で、そこから イギリスの貴族の間で大流行し、紅茶の文化が発達していった。と言われています。
ちなみに、紅茶の関する 深い専門知識や、紅茶の淹れ方をマスターした人が取得できる「ティーインストラクター」と言われる資格なんかもあるみたいです。(日本紅茶協会:ホームページへ)
・紅茶の味の違い
「紅茶」と ひとことで言っても、様々な種類のものがあります。
主に産地によって分かれますが、紅茶もコーヒーなどと同じく「ティーベルト」と言う熱帯・亜熱帯の地域で生育されます。
日本でも静岡や九州地方などで少量作られていますが、ほとんどは海外からの輸入に頼っています。
茶葉を一種類のみ使用したものを「ストレート」と呼び、複数の産地などを混ぜ合わせたものを「ブレンド」と呼びます。
さらに、茶葉自体に香りを吸収させるなどして、香りを付けたりしたものを「フレーバー」と呼びます。
・紅茶の等級
紅茶の茶葉には葉を砕いた際の大きさや、どの部位の葉なのか?といった事を示すための「等級(グレード)」というものがあります。
ちなみに「等級」といっても、値段や産地による希少性を示すようなモノではありませんので、低いからダメとか、高いからどうってこともありません。
あと、統一規格がある訳ではないので 国や、産地なんかによっても若干呼び方が変わってきます。www
まず、葉の砕き方による分類に、
・「フルリーフ」・・・・砕いていない状態の茶葉(葉っぱが丸々一枚って事です)
・「ブロークン」・・・・切断や、砕いた状態の茶葉(葉っぱを横から4等分したり十字に切ったり様々)
・「ファニングス」・・・粉砕した状態の茶葉(小さく平べったい形)
・「ダスト」・・・・・・粉砕した際などに出る粉々の状態の茶葉(ティーパックに使われる)
茶葉を砕けば砕くほど「お湯との接触面が増える」ので、濃い味や、強い味や香りの紅茶になりやすいのが特徴です。
次に、どの部位の葉なのかを分類するのに、
・「フラワリーオレンジペコ」・最上部の芯芽を含む葉(サイズは小ぶり)
・「オレンジペコ」・・・・・・最上部から二枚目の葉(サイズは細長め)
・「ペコ」・・・・・・・・・・茶木の先端から中間の葉(紅茶としてはあまり使われない)
・「ペコスーチョン」・・・・・茶木の中間から下の方の葉(大きめ)
・「スーチョン」・・・・・・・枝の下の方にある葉(大きくてしっかりしている)
葉の部位については、上に付いている葉ほど「若い葉」で「香りや甘味が強い」とされ、下に行くほど「苦みや渋み」を持ったしっかりした味になるとされます。
基本的にはこの二つの等級の組み合わせで どこの葉をどれくらい砕いているのか?を知る事が出来ます。
紅茶の「茶葉のサイズ」は味にも大きく関与してくる大切な要素でもあります。
例えば、茶葉のサイズが統一されていないようなモノや、細かく砕きすぎたモノだと、煮出した際に「渋み」や、「苦味」といったモノが強く出てしまう事になります。
あえて、渋みや苦味を出すためにサイズや種類をブレンドしている場合もありますが、低品質なモノだとそのような味は「雑味」になってしまうワケです。
・紅茶の産地
紅茶は世界20ヶ国以上で生産されていて、特に生産量が多いのが「インド」です。
インドの代表的な茶葉としては、「アッサム」、「ダージリン」、「ニルギル」で、ダージリンティーなんてのは日本でもよく聞く名称ですよね。
日本の硬度の低い水とよく合い、世界最高と称される特徴的な香り(マスカットフレーバー)と、渋みが、日本人の味覚に合うらしいです。
他には、
「インドネシア」の「ジャワ」や、
「スリランカ」の「ウバ」、
「中国」の「祁門(キームン)」や、「雲南(ユンナン)」
なんてものが有名で、その中でも「ダージリン」、「ウバ」、「キームン」は「世界の三大紅茶」と呼ばれています。
・紅茶のフレーバー(着香紅茶)
紅茶に香りなどを加えたモノを「着香紅茶(フレーバーティーなど)」と呼びます。
紅茶の茶葉に色々な方法で香りを付ける訳ですが、その着香方法によって細かく呼び方を分ける事ができます。(これも特に統一規格などはないwww)
・「フレーバードティー」
果実や花などから抽出したエッセンシャルオイルなどを、茶葉に吹きかけて香りを付けたものを「フレーバードティー」と呼びます。
高価なものには天然の香料が使われますが、安価なものは人工的に作られた合成香料などが使われています。
基本的に、紅茶自体に味が付く訳ではありませんので、「香りが変化する」のを楽しむものです。
代表的なものに「アールグレイ(ベルガモットの香り)」や、「アップルティー(赤、青りんご)」などがあります。
ちなみに市販のバリバリに味が付いたものは人工的に味付けされたものである可能性が高いです。
・「センテッドティー」
茶葉が周りの香りを吸収しやすい特性を利用して、茶葉自体に「花や、スパイス」などの香りが強いモノの香りを吸わせて移したものを「センティッドティー」と呼びます。
代表的なものに「ジャスミンティー(花の香り)」、「ローズティー(バラ)」、「ミントティー(ミント)」などがあります。
こちらも紅茶自体に味が付くものではありませんが、下で紹介する「ブレンテッドティー」として販売されている事もあるので、購入の際は混ぜられたモノを確認したほうがよいでしょう。
・「ブレンテッドティー」
紅茶の茶葉に他の花や乾燥させた果実などを混ぜて味や香りを付けたものを「ブレンテッドティー」と呼びます。(「センテッドティー」や「ハーブティー」と まとめて呼ぶ事も多い)
乾燥させた花びら や、果実ピール(果実の皮)を紅茶の茶葉に直接混ぜて、かすかに香りと味や、成分を出す事ができます。
乾燥リンゴが混ぜられた「アップルティー」や、レモンのピール(皮)を混ぜた「レモンティー」、ハーブを混ぜ込んだ「ハーブティ」などもこれにあたります。
ちなみに、わたしたちのよく知っているバリバリレモン味のレモンティはレモン風味をぶち込んだ「レモン風味ティー」なんですよ。(ほとんど香料と酸味料で味付けしてますからねっww)
紅茶に含まれる成分
紅茶にはどんな成分が含まれているんでしょう? 果たして身体にいいのでしょうか…?
まあ、基本的には「緑茶」や、「烏龍茶」と同じような成分が入っています(ハイ、解散!!) が…、酸化発酵によって分子的に変化する成分もあります。
どんな成分があるのか簡単に見ていきます。
・カテキン(ポリフェノール)
ポリフェノールの一種で、緑茶はこのカテキンの含有量が最も多いと言われています。
紅茶の場合は純粋なカテキン自体の含有量はわずかですが、代わりに カテキンが製造工程や発酵によって変化を起こし「テアフラビン」、「テアルビジン」などのカテキン化合物になります。
紅茶の香りや色合いはこれらの物質によるもので、「紅茶ポリフェノール」と呼ばれ、様々な効果、効能が期待できる…とされています。
この変化は、製造工程で茶葉の細胞を破壊する事(揉捻)によって起こり、紅茶のあの茶褐色の色味は植物が自分を守るために出す抗菌性の強い色素の影響だと言われています。
ちなみに、その抗菌作用によって、口臭の軽減、虫歯抑制作用や風邪や、インフルエンザの予防、最近では骨粗しょう症の予防にまで効果があると言われています。
他にも、抗酸化力が高い事や、ガン予防、脂肪の吸収を抑える効果など、ちょっと言いすぎダロ…?とも思いますが…
もともと緑茶や紅茶は 中国では「不老不死の薬」として、イギリスでは「万能の秘薬」として飲まれていた。と言うのですから…、ありえない話ではないかもしれません。
・テアニン(アミノ酸の一種)
これは、お茶特有の成分で、特に「若い芽」に多く含まれ、成熟した芽では極端に減ると言われます。
紅茶は、このテアニンが カテキンに変化する段階で「渋みを出す」んだそうです。
これには、リラックス効果や、睡眠導入の効果、高血圧の改善、記憶力の向上など、様々な効果があるとされます。
特に、テアニンを取ると「α派(アルファ)」が多く出ることが臨床試験で実証されたようで…、テアニンは「リラックスできる成分」としても注目されているようです。
・カフェイン
「カフェイン」と言えば、コーヒーのイメージですが、緑茶や紅茶にも含まれています。
多く取り過ぎると身体に影響があると思われがちですが、かなりの量を摂取しない限り中毒症状などは出ませんし、それを補って余りあるほどの効果・効能が期待できるとされる成分です。
玉露などは、かなりの量のカフェインが含まれますが、紅茶はコーヒーよりも少なめの含有量です。
含有量などは、こちらの記事にも記載してます。
・危険な成分?
紅茶は健康にイイっ!(^^)!。と思わせぶりな事を書きましたが…その品質や、含まれる成分、添加物によってもその認識は当てはまらなくなります。
市販に出回るペットボトルや、缶の紅茶には紅茶の成分より多く「他の成分」が入っている可能性もありますからね。
まず、味を調整する、保存期間を延ばす、などの目的で添加物が使われます。
これは成分表になくても加工前の段階で使われている事が多いので、ぱっと見では分かりません。(キャリーオフされる)
コーヒーの記事でも書きましたが、大量生産品は「全て同じ味に仕上げる必要」がありますので仕方がないのかもしれませんが…。
さらに、渋みを消すために多量の糖分(人工甘味料の場合も)が加えられます。
原材料の欄を確認してください、紅茶よりも砂糖の方が多いとかザラにありますよww
紅茶はコーヒーなどと同様に「抽出する際」に、農薬や、コーティングされた香料などをお湯で一緒に煮出してしてしまう事が問題です。
アップル味やら、ピーチ味やらと書いてあるものは、香料なのか、果汁なのか、ピール(皮)なのか、味付けしている原料を確認しましょう。
出来れば低品質なモノは避けたほうが良いかもしれません。
ちなみに、水出し紅茶は殺菌されてないから危険ンn!!という意見も見つけましたが…それは大丈夫ですwww(紅茶はそもそも殺菌能力が高い茶葉ですし、それ言い出したら熱加工してない植物なにも食べれなくなりますwww)
最近では、ノンカフェインの紅茶なども たまに見かけますが、カフェインの抽出方によっては危険性があります。
カフェインを抜く際に 溶剤なんかを使いますし、抜けた風味を 後から添加しますので、カフェインの危険性だけに目を向けると、他の不要なモノを取り入れてしまう可能性もありますよ。
紅茶葉の抽出方法
最後に「紅茶の抽出方法」についてです。紅茶は抽出方法や、抽出時間によっても味が変わってきます。
基本的には茶葉を直接ポッドに入れて抽出する、葉のままの状態の「リーフティー」と、葉がバラけないようにパック状にくるまれた「ティーバッグ」と呼ばれるものに分けられます。
ここでは、「英国式ゴールデンルール」と呼ばれる、美味しく淹れるためのルールをマスターしておきたいです。www
・英国式ゴールデンルール
その1 :良質の茶葉を使うこと。
まず、自分の好みにあった新鮮な茶葉を用意しましょう。(茶葉を量り売りしてくれるような店があれば 訪ねてみるとよいです)
保管の際は、光、湿気、匂い移りに特に注意して、茶葉はパリパリの状態が良好です。
その2 :ティーポットを温める
対流の起こりやすい丸形のティーポットを使用し、注いだ熱湯が冷めないように必ず湯通しして温めておいてください。(カップも同様に温めるのですが、蒸らしなどをしている間に冷めてしまう場合は紅茶を注ぐ前に温めてください)
その3 :茶葉を正確に測る
1杯分の茶葉の量は「2.5g ~ 3g(ティースプーン中盛り1杯)程度」です。
自分の好みの量を見つけて、毎回同じ味を出せるようにすればよいです。
その4 :汲みたて、沸かしたての水を使う
沸騰したての水を勢いよく注ぐ(1杯分150~160mlが目安)ことで茶葉を「ジャンピング」させます。
ジャンピングとは、「お湯の中に十分な酸素がある」、「高温である(100度前後)」の条件を満たす事で、ティーポット内で起こる「お湯の対流」による茶葉の上下運動のこと。(水中の酸素が茶葉にくっつくことで茶葉が浮かび上がる)
水道水を使うといいとよく見ますが、カルキ臭や塩素が気になる場合は「軟水のミネラルウォーター」をよく振って空気をなじませてから使うといいです。(日本産のミネラルウォーターはだいたい軟水)
その5 :茶葉をきちんと蒸らす
蒸らし時間は、細かい茶葉で「2分半~3分」、大きな茶葉は「3~4分」が目安です。
「ティーコゼー(ポットカバー)」などを使うと温度が下がるのを防げます。
その6 :カップに注ぐべし
ポットの中を軽く ひとまぜして、茶こしを使ってカップに注ぎます。
これで完成です。さて、おいしい紅茶は出来ましたでしょうか?
紅茶をカップに注ぐ際、最後の一滴を「ゴールデンドロップ」と言うらしいです。一番おいしいとされる一滴ですので、残さず注ぎきりましょう。(参考:日東紅茶:紅茶のおいしいいれ方)
まとめとか感想とか
日本人の紅茶の年間消費量は「コーヒー9:紅茶1」といった割合なんだそうです。
紅茶は、ちゃんと作ろうと思ったら「手間がかかる」というイメージが強いのかもしれません。
他にも、食事中に飲んじゃダメ!とか、食後30分は空けなさい!とかヘンテコルールがあるのも原因かもしれません。
タンニンが鉄分の吸収を阻害するから…、なんて言われますが、その割に烏龍茶は「ダイエット効果もある食事のお供」と言われたりします…原料同じなんですがそれは…www
世間では「透明な紅茶」やら、品質の悪い茶葉にアルコールなどの溶媒で香料をコーティングした「なんか別の味がするフレーバーティー」など、変なものもたくさん溢れています。
そういったものが「本物の紅茶」を飲む機会を遠ざけている可能性もあるでしょうね…。
同じ葉から作られる緑茶や烏龍茶などの「お茶」の中でも、レモンを入れたり、フレーバーを付けたりするのは「紅茶」だけです。
そういった多種多様な楽しみ方があるのも紅茶の面白いところと言えます。
イギリスでは「アフタヌーンティー(午後の紅茶)」という習慣があって、午後に「食事を兼ねた喫茶」を楽しむことをライフスタイルとしていると言います。
こういった習慣や、安らげる時間などは「今の忙しい日本人には 特に必要ではないか?」と わたしは思います。
忙しい毎日だからこそ、紅茶のリラックス効果を感じてみるのも良いかもしれません。
ではでは、今回はここまで。また次の記事で会いましょう。
迷った羊の疑問

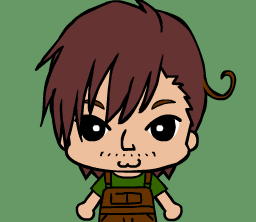
ロイヤルミルクティーは、牛乳に紅茶葉を直接入れて煮出したものなんだよ。(実際には水で煮出してから牛乳を加える)
味が濃くてマイルドになるから とても美味しいよね。

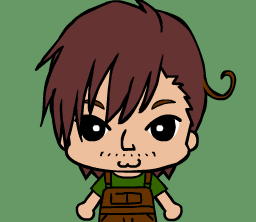
まあ、同じ「茶の樹」から作られるとは言っても、厳密に言えば「緑茶用の茶葉」と、「紅茶用の茶葉」では栽培方法や、収穫時期、土地の気候なんかも変わって来るから…育成の段階から「それに合うように」計算されているモノのほうが美味しいとは思うけどね。

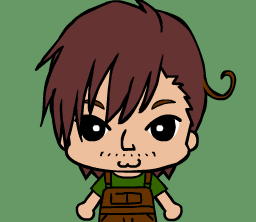
ガラス瓶とかに入れちゃうと、室内光でも1週間ぐらいで梅干しのような酸っぱい香りが出ちゃうからね。
光と、湿度(冷蔵庫はNG)、移り香(匂いが移りやすい)に気を付けていれば長期間保存できて、さらに熟成された味の変化も楽しめるんだよ。
紅茶は既に発酵しているから「賞味期限は厳密に守らなくても大丈夫」って言われているね。

とりあえずイライラした時にハーブティーでも飲もうかな…闇