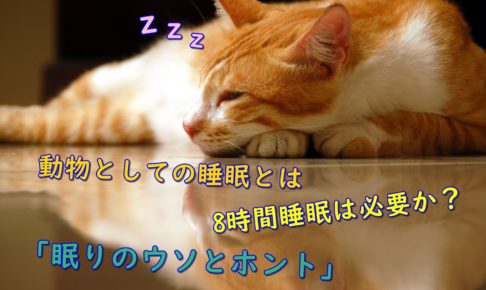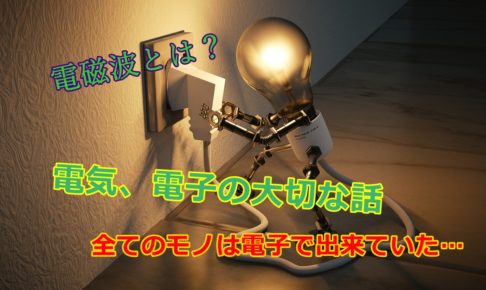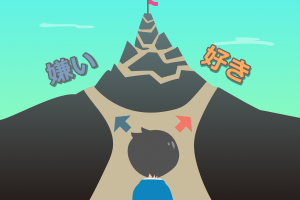ユウサク
あなたは どんな用途で「車」に乗りますか?
買い物に出掛ける際や、友人や家族を乗せて走る、仕事に使う、など、様々な用途に使われる「自動車」ですが。
ここ何年かの自動車の技術の発達、市場の拡大によって、車は便利で、簡単に操作できる、あって当たり前のモノになりつつあります。
しかし、ひと昔前であれば車は贅沢品として扱われ、裕福の象徴として「カラーテレビ、クーラー、自動車(car)の3C」なんて呼ばれた時代もありました。
若者の「車離れ」なんて言葉もささやかれるいま…今後の「車社会」はどのようになっていくのか。
今回はそんな車について、日本のクルマ事情や、イロイロな問題、最近の用語などを まとめていきます。
~もくじ~
日本の「車」事情
今や、日常生活に なくてはならない「自動車」ですが、日本国内での保有台数(ナンバープレートの付いた公道を走行できる車の台数)は年々 増え続けています。
その数は、2014年以降からは既に6000万台を越えていて、単純に考えても「国民2人に1人は車を持っている」という計算になります。
さらに、これに 商業車や、貨物車(トラック)、乗合車(バス、タクシー)、特殊車(パトカー、救急車など)を含めると、国内の自動車は8000万台を超えるそうです。
その保有台数は、交通の便が整っていない田舎は一人当たりの割合が多く、東京、大阪などの交通の便利な地域では少なくなりますが、地域によっては「一家に一台」どころか、「一人一台」に近くなっている。とも言えます。
しかし その反面、冒頭でも書いた「若者の車離れ」や、「贅沢離れ」、「一人当たりの走行距離の大幅な減少」など、車に対する関心の低さなども目立ってきています。
さらに、20年前では「男性ドライバー」が約7割を占めていたモノが、AT(オートマティック)車や、軽自動車の普及などによって、手軽さが増した事もあり「女性ドライバー」の割合が半数近くまで占めるようになっているなど、ここ数年で様々な変化が見られます。
自動車が広く普及し、生活必需品となる事を「モータリゼーション」と言うそうですが、もちろん、車の保有台数が増える事による問題も多く存在します。
・世界に数段 遅れをとる「環境問題への対策」
・原油価格高騰、円安の影響も含めた「ガソリンの高騰や、税金の負担増」
・車の台数に対する「道路の少なさ(渋滞緩和の対応)、税金の使い方」
・車の移動に慣れ過ぎた生活による「健康問題」
・日本国内での自動車の市場が「既に飽和状態」という事実
などなど…。
このように、日本の「車」事情はそこまで明るいとも言えず、いまや上昇期を終え、下降期へと突入していると考えられています。
・電気自動車へのシフト
今、自動車業界は大きな転換期を迎えています。
それは、世界的な「電気自動車(EV)」へのシフト、といった流れによるものですが、日本はこの流れに「大きく乗り遅れている」と言われています。
ドイツなどの欧州各地では、「2030年までにガソリン・ディーゼル自動車の販売を禁止する」といった決議案が発表されていますし、中国などでも大規模な施策や補助金などを出し、2019年以降の自動車販売台数の10%以上を「電気自動車」とするよう 義務付ける法案を発表しました。
日本では、まだ EV化か、ガソリンか(ハイブリッド含む)などの議論が熱いようで、「温室効果ガス排出量を2030年度に26.0%減!」なんて呑気な事を言っているようですが…。
日本の主要産業と言われる「自動車産業」が今後どうなっていくのか見モノではあります。
・新時代の自動車とは?
ヨーロッパ、中国などでは急激なEV化へのシフトが始まっている。と書きましたが、EVと言ってもイロイロな種類があります。
まず、EVとは、electric vehicleの略で「電気自動車」全般を指します。
これは蓄電池に貯めた電力を使って車を走らせるモノで、エンジンの代わりに電動機(モーター)が搭載されています。
ガソリンを使わないため、静寂性が高く、環境に優しいとされ、充電の手間などはありますが、ガソリンに比べて様々なコストが安くつく(モーター駆動なので「吸気、排気、冷却」なども不要)という特徴があります。
日本で主流となっているのは、HV(hybrid vehicle:ハイブリッド自動車)や、PHV(Plug-in hybrid vehicle:プラグインハイブリッド自動車)と呼ばれるモノです。
こちらはエンジンと、電動機の両方を搭載していて、パワーのいる発進時はエンジンを使い、安定走行時は電動機を使うというように、効率的な走行が出来るようになっています。
HV車は、通常のエンジンによる発電と、ブレーキ時の回転などによって発電し、蓄電するので「充電の必要がありません」。
PHVは充電して完全に電気自動車として走行する事もできますが、「エンジンと電動機を積む」という特性上、コストは高くつく傾向にあります。
他にも「天然ガス」、「バイオ燃料」、「水素」などを燃料として走る車も研究されていますが、世界的に見ても「EV化」の流れは止まらないと思われます。
日本では、
・エンジンの技術や産業ラインを崩せない、捨てられない。(吸排気、駆動系の部品メーカーが息絶える)
・コストが安いという事は税収や 利益率が下がる。
・ガソリンを輸入に頼るため需給を切れない。(買わなくなる。という事は、買ってもらえなくなる。という事でもある)
などの経済的な理由も存在するため、なかなかEV化へのシフトは難しいのが現状のようです。
・「自動運転技術」はどこまで行くか?
今まやCMなどでもよく聞くようになった「自動運転」なんて言葉ですが…、
近い未来になれば「完全に手放しで、何もせずとも目的地に辿り着けるようになる…」そんな夢のような話は実現可能なのでしょうか?
まず、自動運転の自動化には「レベル」があり、全てをドライバーが操作する場合は「レベル0」、基本的にドライバーは操作せず、一部の条件下でのみドライバーを必要とする場合で「レベル3、4」、完全に人が乗っていなくても全てをシステムが処理できる状態を「レベル5」と定義しているそうです。(自動運転車:wiki)
世界各国で開発競争が過熱していて、日本政府は2025年を目途にレベル5を目指すとしていますが…。
現状では、高速道路や山道など、整備された障害のない道路などでは十分可能なレベルにまでは達しているようです。
「AI(人工知能)」が全てを判断して、「完全自動化」するためにはまだまだ課題が多いとも言われていますが、どんな問題があるのでしょうか。
・交差点などの複雑な道路状況は判断しきれない。(処理する情報量が多すぎる)
・自動運転と、人間の運転する車が混在した場合、連携が取れない。(人間の動きは予測できない)
・障害物の区別がつかない。(紙袋や、ビニールであっても、動物や、人と同じとして判断する)
・避けられない事故に直面した場合の判断ができない。(トロッコ問題:例、ガソスタに突っ込むか、崖下に落ちるか?の判断)
・天候などによるセンサーの不具合のリスク。(センサーの精度や、故障の問題も)
などなど。
事故を予防するためには「かもしれない運転」をしろ。と言われますよね? ですが、AIに「かもしれない運転」をさせる事はとても難しいワケです…。
人間であれば、お年寄りを見れば「音が聞こえていないかもしれない」、公園が近ければ「子供がいるかもしれない」と臨機応変にスピードを調節できますが、
AIでは潜在的な危険を察知する能力や、それが安全か危険かを判断する能力がありません。
AIが「かもしれない運転」を始めたら、「物陰に人が隠れているかもしれない」「公園から…」「そこの路地から…」「お年寄りだから…」「雨だから…」と、永遠に考え始め「1㎜も進めない」事になってしまうんですwww
他の問題点としては、完全な自動運転の車に乗っていて、事故が起こったら…?いったい誰が悪いって事になるのでしょうか?
それは もう「車のシステムが悪い」って事になってしまいますよね?
つまり、もし事故が起きた時「メーカーが全ての事故の責任を負わなければいけなくなる」なんて事になる可能性もあるワケです。
これから、どんどん発展していくであろう自動運転の技術が どこまで行くのか楽しみではありますが、AIが全てを判断する世界…、恐ろしくもありますね。
クルマの問題イロイロ
ここからは、自動車に関するイロイロな問題や、話題をいくつかまてめていきたいと思います。
・日本の自動車税(税金)
自動車にかかる税金…どれくらいかかるか知っていますか?
購入時はもちろんですが、所有している間も、定期検査の際も、走行するために必要な燃料でさえも、様々な場面で税金はかかっています。
まず、自動車を購入する際に「自動車取得税」が必要になってきます、さらに「消費税」で、購入の際に 二重に課税されます。
維持をするために、車の重量によって決まる「自動車重量税」、さらに排気量によって課税される「自動車税」これも二重に課税されていると言えます。(重量と排気量でなぜ別々になっているのか意味が分かりませんがwww)
走行する際に必要なガソリンの価格に「ガソリン税」と、「石油税」がかかり、なぜか全て ひっくるめた金額にさらに「消費税」がかかります。これは二重どころか三重に課税されていると言えます。(石油税は輸入業者が払うモノだが、結局は価格に上乗せされるので消費者が払っている事になる)
企業から、消費から、資源から、道路利権などから、様々な分野から多くの金を集める事が出来るワケですから…。
自動車産業は、国から見れば莫大な金を生む…まさに 「主要産業(金のなる木)」と言えるワケです。
ちなみに自動車関連の、税金のほとんどは「一般財源」となりますので、道路整備などに使われる事は少ない…と言えます。
国道は狭く、高速無料化、交通整備などは後回し…、日本の主要産業を、国民の利便性のための手段を「集金の道具」としか見ていないのでしょうか?
日本の自動車にかかる税金やお金は、世界から見ても異常なほど高くなっています。(アメリカの49倍、フランスの16倍、ドイツの3倍と言われている)
もし、普通自動車を新車で購入し、通常利用で10年間 使用した場合、購入から、維持、ガソリン税など含めると、「税金だけでもう一台買える」なんて言われています。
車ってとんでもない額の税金を徴収される「贅沢品」なんですよ。
・環境への問題
大体の人は自動車による「環境問題」と聞くと「二酸化炭素」なんかを思いつくのではないでしょうか?
自動車が出す排ガスには様々な物質が含まれています。
代表的なモノで「一酸化炭素」、「炭化水素」、「二酸化炭素」、「窒素酸化物」など。
二酸化炭素などはよく聞くモノですが…、これらは自然界にアタリマエに存在する分子で、自然現象でも多量に発生する可能性のある物質ですので、環境への害はほとんどないとも言われています。(もちろん人体には害はあるでしょうけどwww)
ですが、ガソリンなどの人工精製油には「添加物」などが多量に含まれるので、発生するのは二酸化炭素や、窒素酸化物などの燃焼化合物だけではありません。
単純に見てみてもガソリンには、アンチノック剤、オクタン調整剤、清浄剤、流動性調整剤、氷結防止剤、腐食防止剤、酸化防止剤、表面着火防止剤、摩耗防止剤、着色剤、着臭剤など、様々なモノが含まれています。
これらは ガソリンが燃えた際に消えてなくなる訳ではありませんので、これらの成分は そのまま、もしくは化学反応を起こして変質し、空気中に散布される事になります。(ある程度の熱に耐えるため、熱分解が起こりにくい)
実は、二酸化炭素などよりも、これらの物質が環境や、人体へダメージを与える影響の方が 遥かに大きく危険だ!なんて話もあります。
「二酸化炭素」は環境問題には直結しませんが、こういった人工化合物が撒き散らされている事に変わりはないので、自動車の排ガスは環境に悪い!とは言えるでしょう。
・日本国内の需要が飽和している
冒頭で「国内の一人が一台所有している」的な事を書きましたが…まさに今、日本の自動車産業は「飽和状態」となっています。
つまり、みんな持っているから「買い替える人が少ない」という事です。
こういった問題の背景には、
・車の維持費や税金に莫大なお金がかかる(経済的な理由)
・若者の車への関心が下がっている、車に対して熱狂的な世代の引退など(関心の低下、高齢者の増加)
・国内の道路の量や狭さが車の台数に比例していないため、簡単に渋滞に巻き込まれる(道路整備の遅さ)
・自動車が「電子化、複雑化」し過ぎて 素人じゃ訳わからん(カスタムする楽しさなどが無くなった)
事なんかもあるのかもしれません。
最近では一台の車を複数の人で共有する「カーシェアリング」なんて言葉もよく聞くようになってきました。
国内での需要が冷えかかっている今、日本の自動車メーカーは海外への輸出や、海外生産を中心にした体制を取らざるを得ない状況になっています。
日本の「主要産業」はこれからどうなっていくのか…心配ではありますね。
・運転技術の低下
最近では、自動アシストや、セーフティーなんたらとか、運転をサポートするための機能などが多く装備されるようになりました。
ですが、結局運転するのは「人間」です。
こういった便利な機能は、事故を減らしてくれる!と思いがちですが、それと比例して「安全運転への意識が低下している」と言われています。
つまり、自動車技術の進化に頼ってしまって、自分の運転技術を磨かない、もしくは過信する人間が増えたという事です。(実際に交通事故の件数自体は減少傾向にありますが、交通事故による死亡者数はそこまで減っていない)
自動車に乗るという事は、「鉄の塊を高速で動かす」という事です。
日ごろから安全運転への意識を高め、自分の運転技術というモノにも意識を向けていきたいモノです。
まとめとか感想とか
日本における自動車産業は、日本の「主要産業」とも呼ばれる重要な産業でもあります。
それが低迷しているワケですから…日本の未来はどうなるのでしょうか?www
最近では、中国の驚異的なシェア(生産台数)の増加や、世界的なEV化へのシフト、TPPや、米国との関税の問題などなど…
自動車業界の環境は「常にめまぐるしく変化している…」と言えます。
日本の主要産業は、今や軒並み力を失いつつあります。
自動車をはじめ、家電も、スマホも、農業も漁業でさえも、他国にいいように利用され(主にアメリカwww)、中国の技術パクりとマンパワーによって「日本はどんどん下層へと追いやられている」のが現状です。
日本の産業は国に足を引っ張られて低迷していると言える部分もありますが…www
いまや「中国製」もバカにできない程に技術力を伸ばしてきています。
日本が誇っていた「技術力」も「信頼性」も、そろそろ過去のモノになりつつある時代が来ています。
問題山積みな日本の現状を受け入れて、自動車の事を考える必要があるのかもしれません。
ではでは、今回はここまで。また次の記事で会いましょう。
迷った羊の疑問

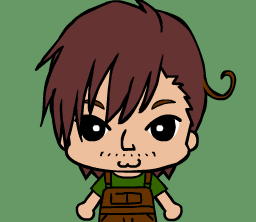
日本のクルマは「品質や、安全性」をウリにしていたワケだから、そういったニュースは影響が大きいよね。
世界的に見て日本のクルマの「品質の高さに対する評価」は確実に低下しちゃってるからね…。
部品や製造を海外で行う事もそうだし、技術力を持った世代が引退している事…なんかも原因なのかな。

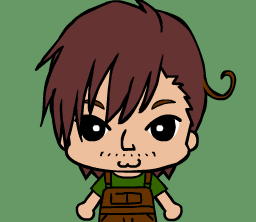
そもそもの「発電して電気を作る段階」で石油、石炭などのエネルギーが使われている訳だからね。
今存在する火力発電とかだと発電の段階でエネルギーをだいぶロスしてしまうから、そのままガソリンとして使った方がCO2排出は少なく済む。なんて事も言われているよ。
CO2削減なんてのは建前で、結局はモノを売るための「温暖化ビジネス」という事なのかもね。

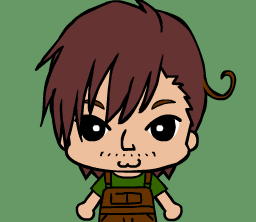
無線通信装置(DCM)を搭載して、同じ搭載車同士だと追従運転できたり、GPSなんかと連動して交通状況の把握や、自動運転も可能になるかもしれない…なんて言われているよ。
まあ問題点として、ハッキングの問題やら、全ての行動がモニタリングできる問題、サーバーダウンした時にどうするのか?なんて様々なモノがあるんだけどねー。

そもそも最近の若者は「免許すら持ってない」んだけどもーwww